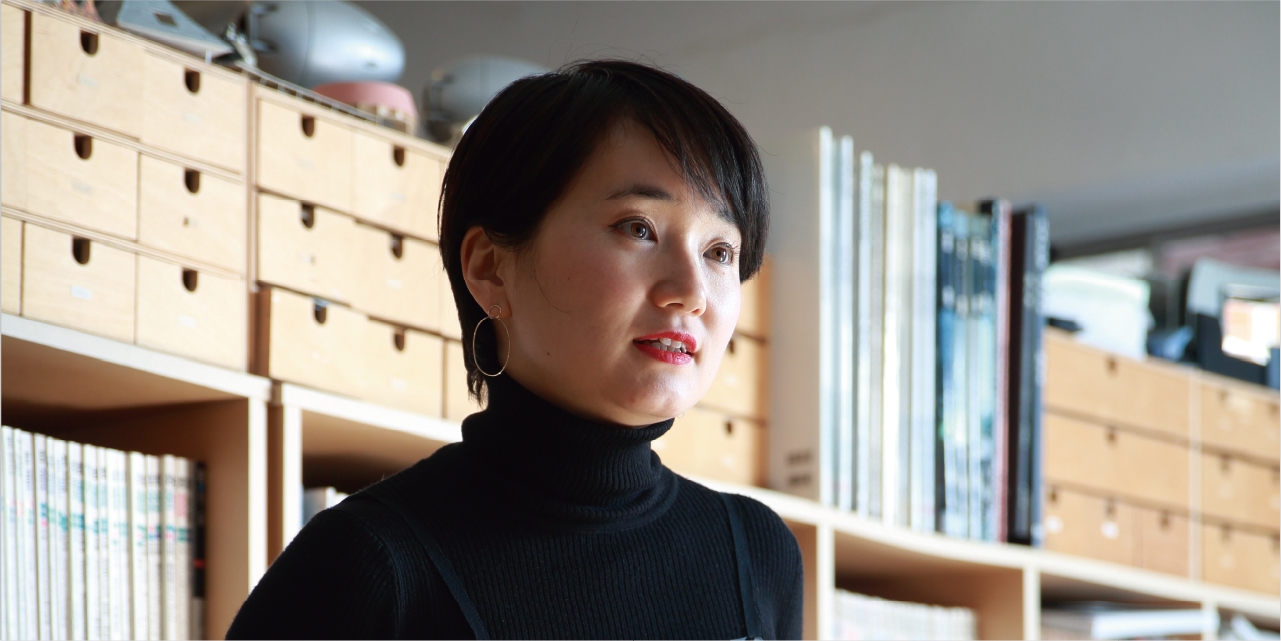
IUIピックアップ VOL.6
土地の時間とつながる建築
インタビュー
大西 麻貴[建築家/ Y-GSA教授]
Interview with
Maki ONISHI
写真|鈴木淳哉(ポートレート)
大西さんには2011年にY-GSAの設計助手として関わっていただき、2017年からは客員准教授という形でスタジオを担当していただいています。2011年に初めてY-GSAに参加したときはどういった印象でしたか。
大西 2011年にY-GSAに初めて参加することになったのですが、直前に東日本大震災が起き、津波で街がなぎ倒されていく様子を目の当たりにして、日本全体が絶望した気持ちに包まれていたように思います。そのときに、Y-GSAのスローガンである「建築をつくることは未来をつくることである」という言葉が、本当に輝かしく感じられたのをよく覚えています。「建築をつくるということは、皆とともに前を向いて歩んでいくことなのだ」と奮い立たされるような気持ちになりました。
大西さんはその後、2017年に今度は客員准教授という立場でY-GSAに戻ってくることになりました。
大西 設計助手の任期を終えてからは、非常勤講師として学部四年生の課題を担当していました。2016年に、一緒に教えていたトム・ヘネガンさんから自分で課題を考えてみないか?と提案して頂き、初めて自分で課題を考えることになったんです。そのときは、劇場をテーマに、ゲーテの「イタリア紀行」や、江戸時代の芝居見物のエッセイなどから課題をつくって、皆で小豆島の農村歌舞伎も見に行って合宿をしたりしてとても楽しかったんです。自分が考えてみたいと思っているテーマを皆に投げかけてみて、一緒に考えてみるということが、こんなにも面白いことなんだと感じました。
2017年にY-GSAに戻ってきて、「土地の時間とつながる建築」というテーマで、小豆島や京都を敷地にスタジオに取り組んできましたが、建築を通して考えられることの広がりや豊かさは、実際に建築をつくることによってのみでなく、皆で建築について考えるというところにもあるのだと感じて、改めて大学って素晴らしいところだなと再認識したところがあります。「土地の時間とつながる建築」というのは、その土地が時間をかけて育んで来た環境と建築が、どのように連続的なものになれるのか、ということだと思っています。環境と呼ばれるものの中には、物理的なものだけでなく民話や神話、人々の習慣や動植物との共存の仕方といった、その土地が培って来た文化や暮らしの感覚も含まれると考えています。
Y-GSAでは教員含めてみんなで話し合うので、誰かがその言葉を言い換えたり思いついたりすることによって、「ああ、そうかも」と視点が変わっていろんなことがつながっていく部分があるかなと思います。
大西 それぞれの先生が単に訓練のための課題をつくっているというのではなく、自分自身が問題にしたいと思っていることを課題にしているのがよいのではないかと思います。それゆえに、お互いの課題に対して、それぞれの建築家が真摯にコメントし合うということが起こっています。今回の最終講評では、建築家の中山英之さんが来てくださって、 乾久美子さんの「再読」という課題への質問をされたときに、乾さんだけではなくて、西沢立衛さんや藤原徹平さんもその課題の面白さや可能性について答えておられました。そのやりとりがあったおかげで、この課題ってこんな風に考えられるのだ、と周りにいる学生も含めて、新たな理解を促す部分がありました。
これまで非常勤講師などでいくつかの大学に伺ってきましたが、講評会にいろんな先生が参加してお互い講評しあうことはあっても、ここまで他の先生の課題そのものに対して深くコメントはしなかった気がしますし、他の先生が指導している学生のことをまさに自分の学生であるように講評するということはなかったように思います。そういうところは、Y-GSAの素晴らしいところのひとつだと感じます。それぞれの課題に対して、建築家自身が真剣に考える姿勢を見て、とても勉強になっています。
大西さんは、東日本大震災の後に、2016年に亡くなられた小嶋一浩さんと東北で一緒に仕事をされていました。
大西 私はそれまで、住宅の設計や小さなインスタレーションしか取り組んだことがありませんでした。震災の後に、小嶋さんや学生の皆さんと宮城県の牡鹿半島の先端にある、鮎川浜という捕鯨で栄えた街に行って、一緒にその街の全体計画を提案することになったんです。そのときに、小嶋さんの視点の大きさ、広がりに触れて驚きました。街全体を俯瞰して、ここにコンクリートの巨大な防潮堤が出来てしまうと、暮らしと一体となった風景が奪われてしまうから、道路と土手のランドスケープを一体にした防潮堤にしよう、など土木と建築を横断する視点、都市計画と建築を同時に考える視点で街のあり方を考えておられました。小嶋さんは常に実践的で、具体的な言葉で街の人を鼓舞していく姿勢もすごいなと思いました。小嶋さんは、なんだか漁師さんの中の親分という感じで(笑)、皆を引っ張っていく存在そのものに迫力がありました。一方で、小野田泰明さんをはじめ、様々な方々と復興全体に対する大きなビジョンや、制度を使いながら計画を前に進めていく方法の議論をされていました。建築家が様々な立場で多くの議論をしながらプロジェクトを推進していく姿を目にしたことは、そのときの自分の能力ではすべてを深く理解することはできなかったと思うのですが、とても大きかったと思います。
百田有希さんとの共同設計事務所「o+h」で多くの賞を受賞しています。「Good Job! Center KASHIBA」が第2回日本建築設計学会大賞やグッド・デザイン賞のベスト100に選ばれたり、尾道市御調支所庁舎のコンペでも最優秀賞を受賞されました。また、コンペで最優秀賞を獲得した多賀町中央公民館も最近完成されたということですね。
ここ数年、公共的なプロジェクトのコンペに参加して勝つということが非常に多かったと思います。公共コンペに積極的に参加しようと考えたのはどういった理由からだったんでしょうか。
大西 ひとつはパートナーの百田が伊東豊雄さんの事務所から独立して、本格的に私たちのチームに加わったことが大きかったと思います。また、「ひがしねのね」と自分たちでタイトルをつけた、東根市の図書館と美術館のPFIコンペに参加したのも大きな影響がありました。これは「PFI」という設計だけでなく運営や施工も含めて考えるコンペだったので、建築をひとつ設計することにとどまらず、街全体の未来について考えようと提案しました。それぞれが、設計・運営・施工といった垣根を越えてともにコンセプトを考えたり、実際に街の人と会って意見を伺ったり、設計と運営が一体であるからこそ生まれる創造的な空間の使い方を考えることが出来るのがすごく面白くて「公共建築ってこんな広がりがあるのだ」と思いました。半年ほどかけて毎週のように打合せする中で素晴らしいチームが出来つつあったのですが、残念ながら二等になってしまい本当に悔しかったんです。その悔しさから、他のコンペにも参加していくようになりました。
このときから「土地の時間とつながる建築」ということを考えていたのでしょうか。
大西 そうですね。東根のプロジェクトでもそうですが、「建築は愛されているのだろうか」ということを、建築家を目指そうと思ったときからずっともやもや考えてきました。新しい建築が生まれるときに、出来ることならばその街の方々が全く興味を持たないというような状況はつくりたくないなと思います。せっかく建物をひとつつくるのであれば、街全体も一緒に考えられるものであってほしい。建築というのは本来そのような、たくさんの人々の気持ちを鼓舞し、勇気づける力を持っていると信じています。多くの建築家が、そうした建築が生まれる喜びを知っているからこそ建築という仕事に就いているのではないでしょうか。私たちは多くの場合、いままで全く縁のなかった街に出掛けていって建築を提案することになる訳ですが、そのときどのようにその土地に根付いた暮らしや文化の豊かさを引き継いでいけるか。それが愛される建築につながると思っています。


複数の賞を受賞している、奈良県香芝市の「Good Job! Center KASHIBA」はどういったプロジェクトでしょうか。
大西 「Good Job! Center KASHIBA」は、障害のある人とともに社会に新しい仕事をつくりだすことを目指すためにつくられた場所です。クライアントは「たんぽぽの家」という、障害のある人のものづくりの力をアートや仕事につなげていくという活動を40年くらい前からずっと自分たちの力でされてきた方々です。私にとっては障害のある人と出会ったり話したりするのが人生の中でほぼ初めての機会だったので、はじめは勝手に遠慮してしまうところがありました。プロジェクトを引き受けることになってすぐ、奈良で開催されていた「HAPPY SPOT NARA」という障害のある人たちの展覧会に行きました。そこで作品と出会うと、きれいだなあと感じると同時にすごくひょうきんなところがあって。アーティストの一人が作品の前でいろいろ説明してくれたのですが、言っていることがすごくおかしかったり、何かよくわからなかったりして、そうすると周りにいたスタッフがみんな「わはは」と大笑いするんですよ(笑)。「何言ってるかわからへんやん!」みたいにツッコんだりしているのを見て、「あ、そうか」と思って。それは奈良のおおらかさでもあるかもしれないし、関西の持っている間違いをツッコむと逆にその人がおいしくなるみたいな文化もあると思うんですけど、笑っていいんだっていうので、言葉以上に感覚で「ここに馴染める!」と感じました。彼らが仕事をしている風景も、それぞれの人がそれぞれの能力を最大限活かしていける環境をつくるというのがコンセプトとしてあって、すごく大きなテーブルで創作している人もいれば、倉庫の片隅に自分だけの場所をつくっている人もいたりする。視察に行った大阪の下町の施設だと、押し入れを改造して部屋みたいにしていて、閉じこもりたいとき押し入れに籠もれるようにしているところもあったりしました。それを見て、このほうが自然だな、いま私たちがみんな同じ向きで机に並んで仕事しているほうが不自然なんだなって思いました。それは一例に過ぎないですが、ある意味で世界の見え方が180度変わるような体験でした。世界の見え方がぐるっと回転して、私たちのいままで持っていた価値判断とは違う方法で、何が豊かなのかを問い直す。そうした価値の反転みたいなことがあったプロジェクトでした。


Good Job! Center KASHIBA © Yoshiro Masuda
いまでもそうした価値の反転について考えることは多いですか。
大西 そうですね。価値の反転というよりも世界の見え方が変わる、という方が正しいかもしれません。先日京都市立芸術大学のシンポジウムに参加したときに、シンポジウムに人だけでなくフクロウとコノハズクがゲスト参加していたんです(笑)。それは「人間だけで話し合うと、どうしても場が固くなってしまうから」という楽しい計らいだったのですが、そのあとお酒を飲みながら京芸の先生とお話ししていたときに、人間と動物、動物と植物の違いというのは一体どこにあるんだろう?という問いかけがあってはっとしたことがありました。私はこれまで、人間とそれ以外の間には大きな線引きがあるものだと思っていましたが、多様性を認めあう社会を押し進めていくと、その先に描かれる究極の理想郷というのは、人間も、動物も、植物も、それぞれに等しくふさわしい居場所がある、とても調和した世界なのかもしれません。それは太古の昔の世界でもあり、ずっと未来の世界でもあるのかなと想像が膨らみました。そのように、いままで自分の捉えていなかった方法で物事を捉え直してみることで、そこにある世界そのものは変わっていなくても、見え方や感じ方が全く変わるものなのだなあと思っています。

大西さんと話していて感じるのは、ひとりの人とかひとつのものや場所が持つ個別の物語を大事にしているということです。オーラル・ヒストリーと言ってもいいのかもしれませんがそうしたことに興味を持っているような気がします。それは小さいときからですか。
大西 そうですね。言葉って、たとえばある言葉とある言葉を選んだときに、その2つを選ばなかった時とは全然違う世界が浮かびあがってくることがありますよね。それを突き詰めていくと詩となるのかもしれないですが、やはり言葉ひとつで全く描かれるイメージが変わることに興味を持っています。また、私はそもそも人と話して、その方の生い立ちや思い出を聞くことが好きなんです。例えば、お祭りで神輿を担ぐ人々を見ていると、それが時空を越えて中世の人々の振る舞いや文化とつながっていることを肌で感じとることがあるように、何気ない人々の記憶の中に過去から脈々とつながってきたことが潜んでいるのではないかと感じています。自分でも気がつかないようなところで、実は過去とつながっていることを知る時に、私たちがいまここにいる理由を感じて深い感動を覚えます。そうやって話を紡いでいくことは、まるで物語のようなところがあります。
本も結構よく読まれていると思うのですが、学生の時はどんな本を読んでいましたか。
大西 京都に住んでいるときは周りに古本屋さんがたくさんあったこともあって、よく通っていました。例えばマルセル・プルーストやヴァージニア・ウルフ、トーマス・マンなど。建築に関する本よりもそうした本を読むことの方が多かったです。
そこからどうやって建築学科にたどり着くんですか。
大西 中学校のときにスペインで(アントニ・)ガウディを見たのがきっかけです。
なるほど。ガウディもカタルーニャの個別の歴史について考えた建築家ですよね。個別の歴史、個別の物語というのが大西さんにとって建築と文学に共通する重要なことなのかもしれないですね。ヴァージニア・ウルフとかマルセル・プルーストとか、そういうナラティブのあり方に対して生的な興味があるというのはすごく感じます。
大西 マルセル・プルーストやヴァージニア・ウルフは目の前にある情景と頭の中に浮かぶシーンを自由に横断しながら文章を紡いでいくところがあると思います。また、ヴァージニア・ウルフは新しい文体をどのように生み出すかということに意識的な人でした。いろいろ思いついたり、頭に浮かんだり、感じたりしていることは、私たちがこうやって言葉に発した瞬間に、すでに比較的構造を持ってしまっているというか、ある程度伝わるように整理されたものになっているのだと思いますが、彼女の本を読んでいて感じるのは、頭の中にあるもっと生な状態がそのまま言葉になっている。こんな瑞々しい書き方があったんだという驚きがあり、それでいてたしかにその通りだと感じられるところが本当にすごいです。
たぶん建築でも文学とも通ずる、相手に意味が通じるために持ってしまう構造というのはある気がします。そしてそのことに意識的な人だけが持ちうるナラティブというものも、またある気がします。
大西 建築についても文学と同じように、新しい文体を生み出す、という視点で考えてみることが出来ると思います。建築は、柱や梁、床や壁や仕上げといったこれまで人間が何千年も使って来たものを使ってつくられるわけですが、それらが単に組み合わせの差異としてだけでなく、そこに生まれる世界の描かれ方そのものがこれまでとまったく違うものである時に「新しい」と感じられるのではないでしょうか。ヴァージニア・ウルフの日記を読んでいると、いろいろな文章の書き方を試しているのですが、例えば「早く書いてみる」という方法によって、何度も推敲した文章とは違う瑞々しさと荒々しさのある文章が生まれた、と自らの文章を分析していたりします。建築でも同じように、どのように建築にアプローチするか、どんな風に建築について考えてみるか、その方法を変えてみることで新しい文体が生まれるのかもしれません。
Y-GSAのスタジオをやる立場になって2年目が終わりますが、関わる立場として今後やってみたいことなどありますか。
大西 寺田真理子さんとも話しているんですけれど、ひとつはY-GSAで本がつくれたらいいなと思っています。設計助手で参加していたときも、当時Y-GSAの校長だった北山恒さんが「大学が出版機能を持って、その思想をどんどん外に配達していくとおもしろい」とおっしゃっていました。去年は山本理顕さんもいらしたり、退官された北山さんもまだ来てくださって講評に参加されたり、すごいことがいまここで起こっている!と感じています。それを何も残さないのはもったいないと思います。いまY-GSAはいろいろと狭間のような状況にあるというか、みんな小嶋さんのことを生々しく覚えていて、その中でまったく新しい体制が始まっているという時期です。いま何を記録したらいいのか、どんな体系で残したらいいのか、どう発信したらいいのかはやってみないとわからないですけど、少しずつできたらいいなと考えています。
また、この四月からは、ルイス・カーンの建築論集をスタジオのメンバーと一緒に読んでみたいと考えています。最近バングラデシュへ初めて行ってカーンの建築を訪れたことをきっかけに、改めてカーンの言葉を読み返してみたのですが、「え、こんなことが書かれていたのか!」と自分の学生時代には全く気がつくことのなかった、一つ一つの言葉から広がる世界の豊かさに感動しています。課題と一緒に、皆で読書会というか、朗読して一つ一つの言葉の意味について議論出来るといいなあと考えています。

1983年生まれ。建築家。2006年京都大学卒業後、2008年東京大学大学院修士課程修了。同年より「大西麻貴+百田有希/o+h」を共同主宰。2011〜13年、Y-GSA設計助手。2017年より横浜国立大学大学院客員准教授。主な作品に「Good Job! Center KASHIBA」、「二重螺旋の家」、「多賀町中央公民館」などがある。
